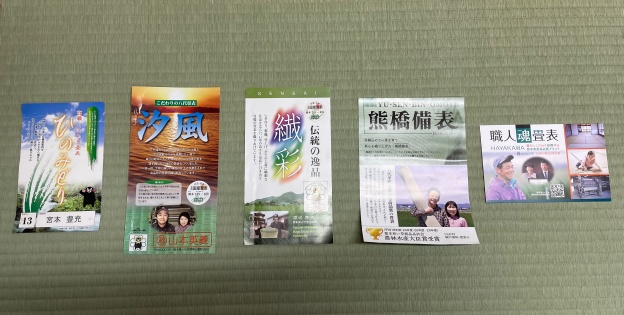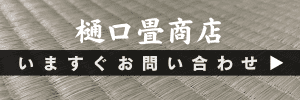今回は畳屋のお金事情を話したいと思います。畳の仕事をしていると皆んなから必ず聞かれることがあります。
実際のところ、畳屋って儲かるの?
この質問は畳の仕事をしているとめっちゃ聞かれます。
先に答えを言います。ぶっちゃけ・・・・普通です。
そもそも畳屋は地域のコミュニティで成り立つ商売。大儲けすること自体、期待することではないと思いますが。
ともかく今回は皆さんが気になる畳屋の懐事情を話していきます。
畳職人の年収はどれくらい?

畳職人の年収は240万〜300万ぐらい。弟子(丁稚)の年収は120万〜180万ぐらい。
240万〜300万ぐらいというのは、あくまで一般的な年収なので、それ以上貰える場合もあれば、それ以下の場合もある。
ただ、弟子(丁稚)の年収は組合?都道府県?国?で決められているので基本的に固定です。
畳職人の年収
「240万〜300万ぐらい」と聞いた時、高いと思ったか低いと思ったかは個人の主観ですが、一般論で言えば2017年度20代の平均年収が346万なので少し低めと言えます。
ですが近年、年収200万以下の働く貧困層working poor(ワーキングプア)が話題になっています。
working poor(ワーキングプア)とは、貧困線以下で労働する人々のこと。「働く貧困層」と解釈される。「ワープア」と省略されることがある。日本では「正社員並み、あるいは正社員としてフルタイムで働いてもギリギリの生活さえ維持が困難、もしくは生活保護の水準にも満たない収入しか得られない就労者の社会層」と解釈される事が多い。
200万以下のworking poor(ワーキングプア)と比べると240万〜300万ぐらいという年収は少なくはないと言えます。
つまり畳職人の年収は普通より少し下ぐらいと位置付けることができます。
畳職人の弟子(丁稚)の年収
working poor(ワーキングプア)に丸っと当てはまる年収200万以下の弟子(丁稚)の年収( ;∀;)
「120万〜180万ぐらい」は笑えます( ;∀;)
とは言え、ほとんどの場合、住み込みでご飯付きなので言うほどお金に苦労した記憶はありません。
一般的にめちゃくちゃ低い年収なので、離職率が高いと思われていますが、内的動機(スキルアップ・楽しい・やりがい)要素が強いので、金額面での離職率は低いです。
私自身も仕事が楽しかったので、年収はアウトオブ眼中でした(気がついたら毎月お金が入ってるイメージ)
つまり年収を上げればインセンティブがはたらくわけではない。内的動機こそ働き方で見つめ直さないといけないと私は思います。
こんな話をすると年収200万円以下で働かしてる企業を擁護しているように聞こえてしまい複雑な心境ですが・・・・。
必ずしも年収200万円以下の人が全員不幸せというわけではない。そこが働き方の難しいところだと皆さんに知ってもらいたいです。
職人の働き方
せっかく畳職人の働き方について触れたので「職人の働き方」について私が思うことを言いたいと思います。
職人で働いて一番疑問に思ったのが、雇用されたことです。
ん?いいことじゃん!と思われるかもしれませんが、職人&経営者の立場から言っても無駄なように感じました。
無駄だと思う理由は職人には忙しい日と暇な日があることです。
例えば、超忙しい一週間を過ごしたとします。もちろん毎日残業です。ですが、次の週の一週間は超暇だったとします。午後にはやることがなくて、サンプル作ったり、最早どうでもいい物を作ったりして時間を潰し過ごすのです。
職人からしたら暇している時間、経営者からしたら残業代が勿体無いですよね。
職人の立場から言うと暇な日には違うお店でお金稼ぎたいし、経営者の立場から言うと給料泥棒に近い感覚です。
みんなが損してる。
そこで職人のフリーランス化を推し進めるべきかと思います。
実際クロス屋などではもうなっているのですが、一部ではなく全体的にフリーランスが当たり前の風潮になったらいいなと思います。
※もちろん、職人&経営者の立場から雇用されるメリットがあることも重々承知しております。
畳屋の利益はどれくらい?

畳屋の利益率は50%を超える!しかし、リピートしてもらうまでの期間が長い。
畳屋の利益率は高い。畳の施工内容にもよりますが利益率が50%超えるのはザラにあります。これは他の製造業と比べるとかなり高い方です。
※製造業の好ましいと言われる利益率は20%〜30%と言われています
ちなみに製造業で利益率がそれだけ低いのは製造する数が多いからであり、利益率20%が残念な数字と一概には言えない。
では、なぜ畳屋はそれほどまでに利益率が高いのか。
なぜ畳屋の利益率が高いのか
畳屋の利益率が高いのには5つの理由があります。
極端に言えば設備投資にお金をかけずに開業できることが大きいです。開業する際に設備投資に多額の資金がかかっていれば費用が嵩み、その分利益が薄くなってしまいます。
また業界の人を知っていれば安く、もしくは無料で道具などを揃えることができることが理由になります。
昔何かの記事で「畳屋は設備投資にお金がかかる」と言いましたが、機械さえ買わずに貰うことが出来れば他の製造業より圧倒的に「お金がかからない」と言えます。
また原価が安いのも利益率が高い理由のひとつです。原価を明かすことはできませんが、畳の材料であるい草は農作物なので、他製造業の原価に比べて格段に安いものになります。
このように「お金がかからない」「原価が安い」「人件費がない」などの理由から驚くべき利益率になるのです。
なぜリピートしてもらうまで期間が長いのか
ここまでの畳屋の利益率は高いという話をして、魅力的な商売だなと思った方もいらっしゃると思います。
現実・・・そう上手くはいきません。
畳屋最大のデメリットはリピートしてもらうまでの期間が長いことです。
例えば飲食店のリピーターは一ヶ月に1〜2回くらい来店。常連客になれば一週間に1〜2回訪れる方もいるでしょう。
それに比べて畳は早くて5〜7年くらい。上等品を納品していれば10年くらいは畳替えをしません。もはやリピーターという言葉が当てはまるのかどうかもわかりません。
地域密着でこの期間の長さは、決して魅力的な商売とは言えないでしょう。しかし、なぜリピートしてもらうまでの期間が長いのでしょうか。
それは畳の優れた耐久性と適切な交換期が認知されていないことが原因と思われます。
20年使っても痛んでない畳屋泣かせの畳もあるぐらい優れている耐久性。お客様に丈夫なものを提供している証ではあるので何も言えない( ;∀;)
「痛んでいても使えるから」「いつ畳替えすればいいかわからない」といった畳替えの適切な交換期が認知されていないこと。
これは私たちの努力が足りてない。これから改善していく必要があります。
畳屋の年収はどれくらい?

街の畳屋さんの年商はだいたい1000万〜1億円くらい。年収となるとお店によって違うので出しようがない。
街にある畳屋、おじさん一人で営んでいる場合は年商1000万くらいが普通だと言われています。
ちなみにおじさん一人で稼げるMAXは年商2800万と聞きました。
計算方法は知りません(笑)ただ、これは畳屋の材料商から聞いた話なので、ある程度信憑性はあるかなと思います(´ε` )
職人を雇っている畳屋さんは年商3000万〜5000万円くらい。職人と従業員(営業や事務など)雇っている畳屋さんは年商5000万〜1億くらいと言われています。
街の畳屋という枠ではこれが限界の金額。もっと稼ごうと思うなら法人化して工場は拡大、機械は生産ラインを入れ大量生産にして、店舗数を増やす必要があります。
その結果、年商60億売り上げている畳会社もあります。
なぜ年収が出しにくいのか?
年収が出しにくい理由は3つ程考えられます。
他の個人店の経営に詳しいわけではありませんが、畳屋以外も同じような理由で年収が出しにくいのかなと思います。
確かに個人事業になってお金に対する考え方は明らかに変わりました。
今まで毎月もらえるお金は全部自分のお金と思っていましたが、全部お店のお金だから・・・って思うようになったのです。
銀行にお金入れておかないと不安というのもあるんですがね♪(´ε` )
最後に
いかがだったでしょう。
畳職人や畳屋の年収について参考になりましたか?
一般的な人からしたら仕事を選ぶ上でお金は大切な位置付けだと思います。そうでなければ生活出来ないし、欲しい物を買えません。
衰退産業にある畳業なんて誰も選ばないでしょう。そんな業界に私は18歳から身をおき、今も大好きな仕事として日々励んでいます。
でも、もしこの世にお金なんて存在していなければ、皆さんはどんな仕事を選んでいましたか?
年収で選べません。成長産業か衰退産業かでも選べません。
そんな役に立たない情報なんかどうでもよかったはず。
だから最後に言ってしまえば、ほんっとどうでもいい記事の内容だったと私は思います。
それでも読んでいただきありがとうございました。