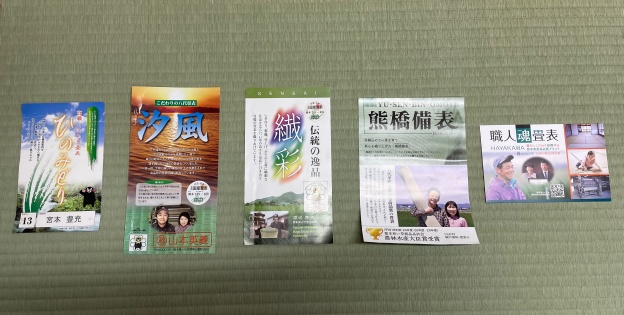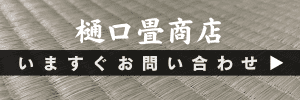こんにちは!畳職人の樋口です!
畳の上でゴロンとなってお昼寝すると気持ちいいですよね。日本の夏って感じで。
どうやらそれは人間だけじゃなくて、猫も気持ち良いらしいです。

そんな人間にも猫にも愛される畳ですが、現在進行形で需要が下がっています。もしかしたら畳の存在を知らない子供もいるかもしれません。
そこで今回は、畳のことを知ってもらうために畳とは何か?畳の効果とは?畳の歴史とは?など畳について詳しく語りたいと思います。
畳について知りたい!という方々の参考になれば幸いです。
このテーマについては、YouTubeでも語りました。動画が良い方はこちらをどうぞ。
・畳の効果とは?
・畳の歴史とは?
・茶道と畳
・これからの畳業界と畳
畳職人が語る畳論

畳論のはじめに、そもそも畳とは一体何なのか。どういった敷物なのかから紹介していきます。
畳とは何か?

畳とは、藁床にイ草を編んで作った畳表を縫い付けて両幅に畳縁を縫い付けたものを一般的に畳と呼んでいます。とはいえ、最近では藁床の代わりに建材床が主流になり、天然い草の代わりに和紙表や化学表が使われることも多くなりました。
他にも畳縁が付いてない縁なし畳や敷き込まないタイプの畳(置き畳や貼る畳など)など、従来の畳とは違う使い方の畳も畳と呼ばれているので、畳の定義は広いものと考えてもらえればと思います。
▼和室についてはこちら:和室とは何か?和室とはどんな部屋?|畳職人が考える和室論
ただ、どんな畳においても共通して言えることがあります。それは癒しを目的に作られている敷物だということです。お昼寝する際、畳の上にゴロッと横になると気持ちが良いと感じるのは、適度な柔らかさを考えて畳が作られているからであり、畳はお客様にとって癒しの代名詞でなければならないと私たち畳職人は思っています。
畳の効果とは?
畳の癒し効果というのは何も主観によるものではなく、科学的に根拠があるものになります。その一つが畳の香りです。
畳の香りは人間をリラックスさせる効果が期待できる
畳の香りには紅茶に主に含まれるとされるジヒドロアクチニジオリド、バニラに含まれるとされるバニリン、森林浴などで放出されるフィトンという物質が畳(い草)には含まれているのですが、これらには人間をリラックスする効果があると言われています。
畳の香りを嗅ぐとなんか癒されるなぁ。には理由があったわけです。
実は、畳の香りによるリラックス効果は、仕事や勉強にも良い影響を与えます。
ある塾で小中学生を対象に、勉強部屋に畳を敷いて、計算問題を時間内にできる限り解いてもらう実験を行ったところ、解答数が全体で14.4%も伸びました。これは、い草のもつリラックス効果と吸音性による集中力の持続効果が要因だと考えられます
北九州市立大学の森田教授の研究によれば、勉強する時に畳を敷いた部屋とフローリングとでは、解答率に差が生じたという研究結果を発表しました。
畳の香りのリラックス効果は子供達にも良い影響を与えているということなので、幼い子を持つ親御さんは一度畳の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
▼置き畳はこちら:置き畳の人気おすすめって何?|置き畳のメリットとデメリットを解説
畳には抗菌作用がある
イグサは腸管出血性大腸菌O157 ,サルモネラ菌,黄色ブドウ球菌などの食中毒細菌,バチルス菌,ミクロコッカス菌などの腐敗細菌に対して抗菌作用のあることが明らかとなっています。
〜中略〜
最近の研究では肺炎の原因となるレジオネラ菌に対しても抗菌作用が認められました。このような事実からも畳は天然の抗菌素材といえます。 ー北九州市立大学
床材で抗菌作用があるものと言えばヒノキのフローリングが有名ですが、畳にも腐敗細菌に対しての抗菌作用が確認されています。
だからと言って、畳を舐めて良いとか床に落ちた食べ物を食べて良いと言うわけではありませんが、子供がいる親御さんにとっては安心の床材なのではないかと思います。
畳には足の匂いを軽減する効果が期待できる

私たちの大学では足から,この微生物を取り出し,わずか2% のイグサの抽出液を加えたところ,微生物群の増殖を抑える作用について発見しました
そもそもなぜ足が臭うのか。一つは足の皮膚などにいる雑菌の繁殖が原因と言われています。大量に汗をかくことにより、菌が増殖し、臭い匂いを生み出しているのだそうです。
畳の材料であるい草は、そういった微生物群の増殖を抑える作用があります。菌の増殖を抑えることで足の臭いの軽減に繋がると言われているのです。ただ、これはまだ研究途中であり、今後さらなる研究が求められます。
▼い草インソール:【い草インソール】靴の臭いが気になる方に人気おすすめイグサの中敷
畳は吸湿効果がある
畳は部屋中にある湿気を吸い取ってくれる効果をもっています。その吸湿量は畳一枚で牛乳瓶約一本半分(約300ml)程度だと言われています。
しかもただ吸い取るだけではなく、乾燥した空気の場合には吸った水分を放湿してくれます。まさに畳は自然の除湿機であり、加湿器なのです。
畳は有害物質を吸着する効果が期待できる
畳(い草)にはホルムアルデヒドやタバコの匂いなどの有害物質を吸着してくれる効果が期待できます。ホルムアルデヒドは私たちの身近で使用されている化学物質であり、シックハウス症候群の原因の一つだと言われているほどの有害物質です。
それらを吸着してくれる畳はまさに自然の空気清浄機だとも言えるでしょう。
畳の歴史とは?

畳について興味ない人にもこれだけは伝えたい!!!畳の歴史、めちゃくちゃ長いよ!!!って。一説によれば、畳の登場は今から約千三百年前。天皇陛下や皇族の方々、王族、貴族などが畳を使っていたと言われています。
712年頃に太安万侶(おおのやすまろ)によって編纂された古事記にも菅畳八重・皮畳八重と記述があり、畳の存在は確認されているのですが、それ以前の畳の記録に関しては無く、ほとんどよくわかっていません。
現存する日本最古の畳は、奈良県の東大寺正倉院にある御床畳(ゴショウノタタミ)と呼ばれる畳で、聖武天皇が使ったとされています。御床畳の特徴は、マゴモを4〜6枚くらい重ねて畳床を作り、手織りで織ったイ草を縫い付けて、錦の縁を付けたものであり、現在一般的に言われる畳とは違った使われ方をされていました。
その使い方は主に寝床であり、今で言うベット代わりだったのです。この頃の畳と言うのは、家具的な役割で使用されることがほとんどだったと言われ、畳を敷き込んで使ってはいなかったようです。

私たち畳職人の仕事に有職畳と呼ばれる仕事があります。有職畳とは、まさにこの時代から今まで続いている伝統的な畳のことで、宮内庁の行事や高貴な社寺に納められています。

▼畳職人の仕事についてはこちら:畳職人になるにはどうすればいいの?|畳製作一級技能士になるまでの過程
このように畳は日本の歴史と共に歩んできたわけですが、畳と言うと必ず中国起源説が飛び出すので、畳の歴史の最後に畳は日本固有の文化であることを皆さんに伝えていきたいと思います。
まず、なぜ畳の中国起源説が飛び出すのかと言うと、それは上敷き(ゴザ)と関係します。ゴザとは、い草を編み込んで作られた敷物のことで、その歴史は二千年を超えるとも言われています。
そもそもい草の発祥地はインドだと言われ、それからシルクロードを経て中国へ入り、日本に渡ってきたというのが通説です。それ故に、い草を編み込んで作られた上敷き(ゴザ)も中国から伝わったのではないかと言われています。
この点についても異論はありますが今回は100歩譲って、い草の上敷きが中国から伝わったとしましょう。
▼異論はこちら:【歴史】畳が広まった理由は茶道?|日本史&畳年表でみる畳の歴史
しかし、それをもって畳は中国起源とはなりません。そもそも上敷き(ゴザ)と畳は全くの別物であり、定義も明確に違います。(過去も現在も)
皆様だってそんなこと理解していますよね。畳を頼んで上敷きが来たらクレームものでしょ?つまり畳と上敷きは違うものなのです。中国から上敷き(ゴザ)が伝わったから畳も伝わったというのは乱暴な話であり、全く根拠のない空想であると私は思います。
ですので、皆様にもこの事を伝えたいと思い最後に記述しました。
▼上敷きについてはこちら:【国産い草】子供のお昼寝に人気!夏におすすめの寝ござを紹介
茶道と畳

畳論を語るのであれば、茶道も語らざる終えない。私はそう思っています。
これまでの畳は皇族、貴族が使う敷物でした。その後、鎌倉時代に武家が権力を持つと彼らの間で畳は広まっていきます。とはいえ、一般家庭にはまだまだ使われるような敷物ではありませんでした。
では、畳が一般家庭に広まった理由とは何なのか。それこそが茶道です。それには、ある一人の男が関係しています。
遡ること室町時代、その頃親しまれていた茶道と呼ばれる遊戯は現在の茶道と似て非になるものでした。その面影は全く何もなく、高貴な者たちが自分の茶碗自慢をしたり、闘茶と言って飲んだ茶の銘柄をあてる博打として親しまれていました。
それを正したのが茶道の祖、村田珠光(むらたじゅこう)です。村田珠光は茶会での博打、飲酒を禁止し、茶の精神を正しました。それが侘び茶(茶の湯の一様式)の源流となります。
その村田珠光の想いを受け継ぎ、侘び茶を完成させたのが皆様ご存知の千利休になります。千利休は畳を敷いた茶室を世間に広めてくれました。それがキッカケとなって一般家庭に広まっていったと言われています。

ウェキペディアより引用
ここでお茶室の仕事について紹介したいと思います。
お茶室の仕事は一般的な畳に比べてかなり難易度が高い仕事になります。特に畳の寸法と割付はかなり重要で、私的には社寺の紋縁より難しいと感じます(仕事を比べてはいけませんが・・・。)
一体何がそんなに難しいのか。

一つは畳の目です。
大工さんとかお茶を習ってる人でないと畳の目?と言われてわからないと思いますが。畳の目とは、畳の谷の部分に畳縁が被っている姿を言い、「畳の目に乗っている」と表現されます。
なぜ茶道で畳の目が大事かと言うと、お茶では畳の目によって道具の置く位置などが決まります。これは流派にもよるので一概には言えませんが、もし畳の目がズレていたらどこの流派関係なく大変なことになってしまいます。

こちらは64目の備後中継ぎ表で作った畳になります。64目の畳表を使うと京間で施工した場合、上前だけでなく下前も畳の目に乗ることができます。
とは言え、畳は部屋ごとに寸法が違いますし、地震やら老朽化やらで部屋に歪みが生まれてしまいます。つまり、一般的な畳で用いる方法である下前で歪みをつけて対角を出すことができないため、畳の丈で対角(シミズ)を消して一枚に対して歪みをつける手法を使わなければなりません。(通称、掛けシミズ法)
これがまぁ難しいこと。
こういった難しい畳が江戸時代に入ると求められるようになり、畳職人にも技術力が求められるようになっていきます。お茶室に畳を敷いていなければ、今の畳職人はこんなに技術力が高くなかっただろうし、技術や技能について考えなかったのではないかと私は思います。
茶道のおかげです。
畳論の一番最後にこれからの畳業界と畳について語りたいと思います。
これからの畳業界と畳

悲しい話になりますが、平成に入ると急激に畳の需要が減少していきます。
その減少レベルは恐ろしいほど。平成元年まであったイグサ農家さんは、8578(戸)ほどだったのですが、平成28年には522(戸)まで減少しています。およそ28年間で約1/16。現在もなお減り続けている状況です。
では、なぜこれほど畳の需要が減少したのか。その原因はいくつか考えられます。
・新築の注文住宅の減少
・後継者不足問題
平成に入り高度経済成長が終わりを迎えると、私たち日本人のライフスタイルや消費傾向にも変化が現れます。核家族化が進んだり、ワンスペースで生活したり、新築の注文住宅ではなく建売ハウスが好まれるようになりました。
また、若者は肉体労働や職人の仕事よりIT系のデスクワークを好むようになりました。その結果、後継者不足で畳屋は次々と廃業していったのです。
とは言え、今更嘆いてももう進んでしまった針は戻せないわけで、これから畳業界はどうしたらいいのか。畳はどうなっていくのがいいことなのか。考えなくてはなりません。
ネットを見ていると新しい取り組みをしている畳屋さんも存在します。応援の意味も込めていくつか紹介します。
畳のモダン乱敷き
多様な形の畳
日本畳楽器製造
他にも紹介したい畳屋さんはいくつもあるのですが、また別の機会にしたいと思います。で、私個人的には畳業界の為に何をしたらいいのか。最後にそれを語りたいと思います。
これまで色々な畳の話をしてきて気づいた方もいるかと思いますが、畳という敷物は時代に応じて革新してきた敷物であるということがわかると思います。
まず、平安時代。畳は家具的役割として高貴な方に使われてきました。その後、鎌倉時代。武家の皆さんに勉強する部屋として使われてきました。そして、江戸時代。茶室に畳が敷かれたことによって一般の人々に使われるようになりました。
畳の形状にほとんど変化はありませんが、確かにその時代において使われ方に変化が見受けられます。
私はこれを使い方の革新と呼んでいます。この使い方の革新は日本の伝統産業と呼ばれるほとんどの業種に起きていることで、特に昨今話題の印章もその一つです。
かつて印章も一度は滅びかけました。しかし、戦国時代の将軍達に気に入られて印章は復活を遂げたのです。姿形は変わらずとも時代が求めている使い方に浸透することが出来れば、それは革新となる。私はそう信じています。
最後に
私たちは間違いなく過渡期にいる。それは急速に進むテクノロジーの進歩からの弊害であることは間違いありません。
とは言え、泣き言言っていたって始まらないし、何か変わるわけでもありません。で、あればそれを使いこなして時代を生きる事こそ、今やらねばならないことではないかと私は思います。
読んでいただきありがとうございました。良かったらシェアお願いします。