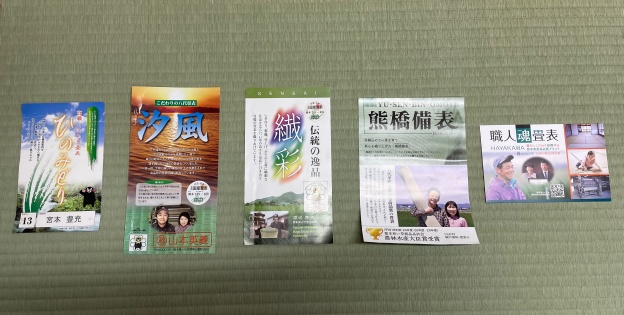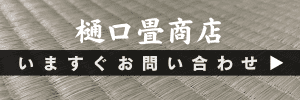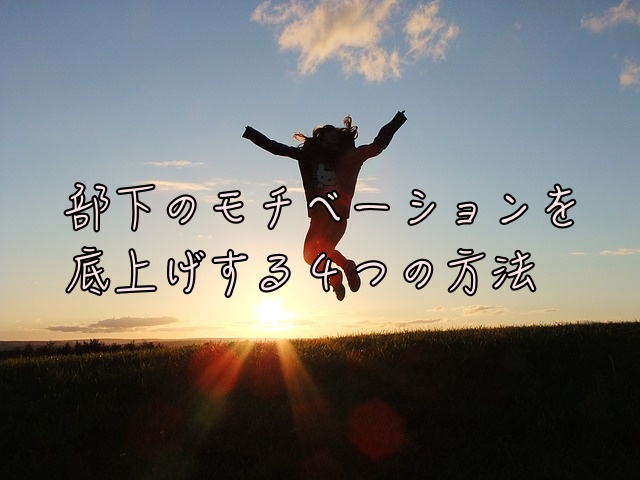
こんにちは!
畳職人の樋口です。
仕事が忙しい季節。
少しでも仕事を早く終わらせて、自由な時間を過ごしたいと思いますが、現場で働く部下達はだらだら仕事をしていて、一向に終わる気配がしない。
「なんで私だけ頑張らないといけないのだ?」とイライラして自分のモチベーションを下げてしまう結果になったら最悪です。
そこで、今回は部下のモチベーションを上げる為に必要な4つのことを紹介します。
モチベーションとは何か

 「モチベーション」と言う言葉。皆さんも普段使っていますよね?
「モチベーション」と言う言葉。皆さんも普段使っていますよね?
まず、モチベーションとはそもそも何なのかを説明したいと思います。
モチベーションという言葉はビジネスシーンでは「動機付け」という意味で使われています。
会社でモチベーションという言葉を使うなら仕事でのやる気を指しますし、野球でモチベーションという言葉を使うなら練習のやる気を指しています。
その仕事でのやる気というのは、良いパフォーマンスを生み出す為には必須なことであり、チームがプロジェクトを成功する為の基礎だということです。
モチベーションを上げるならお金?
「モチベーション上げるなら賃上げしたら良いじゃん」って言う会社組織での話をします。
モチベーションを上げるなら賃上げ(業績連動型の報酬制度)すれば比例して上がると言った説をよく耳にしますが、実際に導入した企業で「仕事への愛着」「従業員満足度」が上昇したという事例はあるにはあるのですが、それだけでは限界もあります。
賃上げは無限に行えるモノではありませんし、賃上げは経済状況に左右され、不況ならどんなに頑張っても上がらない可能性だってあります。
また厄介なのがミレニアル世代の人間です。彼らは報酬が良くても仕事の環境によってはモチベーションを上げてくれません。
ミレニアル世代は消費することに消極的な世代で、子供の頃から不況しか知りません。なので、現在の報酬より今後長い間使える技術取得の方に重きをおいているように感じます。
私たちも同世代で、ミレニアル世代の気持ちはよくわかるが、扱いづらく難しい世代だなと感じます。

そしてもう1つモチベーションを上げる方法としてよく言われるのが、労働時間の短縮です。
労働時間を短縮すると、モチベーションが上がり作業効率が上がるというのですが、これには疑問があります。労働時間を語る時、人によっては労働時間を短縮して欲しくない人がいることを忘れないで欲しい。
働き方で思うことは人それぞれ、むしろ企業が嘘偽りなく実際の労働環境を提示すればいいだけの話。魅力的な企業ぶって良いイメージで提示するから問題がややこしくなっていると私は思います。
そもそも仕事のモチベーションを上げたいのに労働時間を短縮してしまうというのも変な話で、例えば、学校の文化祭の準備でクラス全体が盛り上がっている時に、そろそろ帰りなさいと言われ「気分が乗ってきたのに(T . T)」となるのと同じ状況だと思います。
また最近では時短ハラスメント(ジタハラ)という言葉が話題を集めています。これはまさに「残業するな帰れ」と急かされることで、日中の仕事にプレッシャーがかかり逆効果になった例です。
このように言うと「プレッシャーがかかるのは良いこと」だと言う人がいますが、プレッシャーには良い効果をもたらす場合と悪い効果をもたらす場合の二種類あることを忘れてはいけません。

基本的に自分自身で与えたプレッシャーは良い効果をもたらし、プロジェクト成功のエンジンになってくれることでしょう。例を出せば、ビルゲイツの事例が有名です。
ビルゲイツは、まだBASICの形も無い段階でMITS社に「Altair 8800用のBASICインタープリターを開発した」とハッタリをかまし、話を繋げました。
自分を追い込んだことで開発には一応成功し、MITS社と契約を結ぶことが出来たんです。このように自分自身を追い込みプレッシャーをかけることで、成功の足がかりにしたことは間違いないでしょう。
しかし、プレッシャーがかかることで悪い効果をもたらす場合もあります。みなさんおっ察しの通り、他人から押しつけられたプレッシャーです。
モチベーション上げるどころの話ではなく、仕事が嫌になって会社に来なくなることだってあります。いや、最悪の場合、自殺だって考えられます。
有名な電通の事件もそうですし、私の友達も自殺しました。
「プレッシャーをかける」という言葉は、よく咀嚼したうえで発言してほしいと考えます。
4つの欲動


モチベーションに関連する4つの欲動について紹介します。
ハーバード・ビジネススクール名誉教授のポール・R・ローレンス氏とニティン・ノーリア氏は次の4つの欲動が我々人間の行動の全ての基礎になっていると述べています。
①獲得への欲動
・社会的地位など無形なものも含めて、稀少なものを手に入れること
「隣の芝生は青く見える」の言葉通り、私たち人間は相手の所有物や地位などを比べてあれが欲しい、これが欲しいと欲望に駆られる生き物です。
その欲求には限界がない為、満たすのは事実上不可能とされています。
その為か「強欲(グリード)」はキリスト教で七つの大罪として人間の犯してはいけない大きな罪として教示されています。
②絆への欲動
・個人や集団との結びつきを形成すること
金八先生曰く「人という字はヒトとヒトとが支え合ってできてる(事実は人の形を表した象形文字)」と教えています。
人間は繋がることを求め、親や血族だけに留まらず、組織、チーム、仲間といった血の繋がりを超えて広がりをみせます。
これが満たされていると愛や思い、前向きな感情になりますが逆に満たされていないと孤独感や閉塞感、否定的な感情になります。
人間の不安の多くはこの欲動が関係していることでしょう。
③理解への欲動
・好奇心を満たすことや自分の周りの世界をよく知ること
「科学において好奇心は不可欠な前提条件」この言葉を残したのはドイツ、ハイデルベルグのBioMed Xで腫瘍免疫学研究グループの責任者を務めるリー・キム・スウィー博士です。
私たちが子供の頃に思った疑問。「青空は何で青いのか」「星はどうして光っているのか」「どうして生命は誕生したのか」自然の不思議が気になって「教えて!」とよく親に尋ねたもの。
大人になったらわかったような気になって科学に関しての理解への欲動が失われてきたような・・・・
④防御への欲動
・外部の脅威から我が身を守り、正義を広めること
人間が改革に抵抗があるのは防御の欲動によるものと言われています。
防御の欲動とは本能的にビジョンや信念などを外敵から守ろうとすることで、さらに正義を求め、具体的な目標と鮮明な態度を示し、それを表明できる組織を生み出したいという希望になります。
以上、4つの欲動を基盤にして、モチベーションを上げる為にはどうすればいいのかを考えていきたいと思います。
モチベーションを上げよう

これら4つの欲動を参考にしたモチベーション上げる4つの方法を紹介します。※ハーバード・ビジネススクール名誉教授のポール・R・ローレンス氏とニティン・ノーリア氏の思考を参考にしました。
①獲得への欲動:報酬制度
獲得への欲動を満たす為には、上記で紹介した通り、賃金(業績連動型の報酬制度)が有効です。
また稀少な地位として役員、執行役、取締役など昇格もモチベーションを上げるのに効果があります。
しかし、報酬制度も昇格も行うのに限界がある反面、人間の欲動には限界がないことから周りの人と比較させて少しずつ上げるのがよいでしょう。
②絆への欲動:企業文化
4つの欲動の中で特に重要なのが絆への欲動です。
会社は組織で、できています。もし一緒に働けることを自慢したくなるようなチームを作ることができれば一人一人のモチベーションは高くなることでしょう。
例えばGoogleには年間約200万通以上の就職申込書が送られて来ます。
それは「Googleで働きたい」と思って申し込みをするのだが、「スキルアップできる」という気持ちに次いで「Googleのような世界的企業に勤めるトップレベルの人たちと一緒に働ける」という絆への欲動も人間にはあります。
それがモチベーションを高くすることに繋がります。
③理解への欲動:職務設計
これは絆への欲動で出た「スキルアップ」と繋がる話ですが、自分の成長ができる場所ほどモチベーションは高く保つことが出来ます。
もし単調な仕事をずっとさせていたら社員のモチベーションは上がらずハイパフォーマンスを生み出すことは出来ないでしょう。
社員に権利を与え、責任ある仕事を任せることこそハイパフォーマンスを生み出すことでしょう。
④防御への欲動:業績管理と資源配分プロセス
改革に対して反対する人は今の現状に満足している、リスクを取りたがらないことから防御反応が起こり保守的になってしまいます。
彼らの防御反応を起こさせない為にも先の見えない状況を作り出さないようにし防御反応を沈めるような説明をする必要があります。
最後に
いかがだったでしょう。
部下のモチベーションを上げることがリーダーとしての役割かと思いますが、上記記述通り私を含めて、ミレニアル世代は扱い方が難しいと思われます。
私自身も部下の立場に立って部下のモチベーションを上げることに尽力しましたが、なかなか上手くはいかなかったです。その時に出会ったのが今回参考にさせていただいた本「動機づける力」です。
世界でも有名なハーバードビジネススクール名誉教授ポール・R・ローレンス氏とニティン・ノーリア氏の提唱した説ということで、これはビジネスに活かせるぞと思った次第です。
それから部下のモチベーションを上げられたかは不明ですが、仕事を通しての関係性は順調に進んだのではないかと思います。
 |
動機づける力新版 モチベーションの理論と実践 (Harvard business review anthol) [ ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス編集部 ] 価格:1,944円 |
![]()
「動機づける力」については新しい発見が必ずある本だと思うのでオススメです。
読んでいただきありがとうございました。