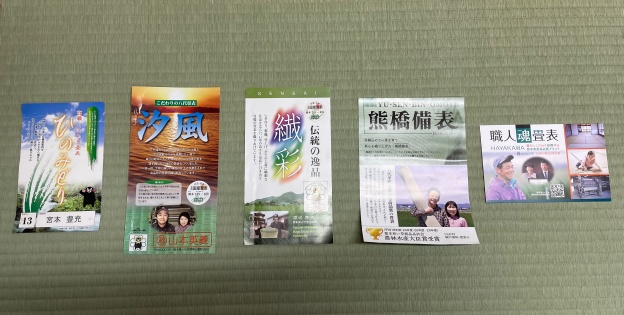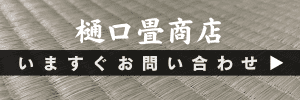今回の記事は日本の働き方での問題点である「長時間労働」なのにもかかわらず「労働生産性が低い」ということに焦点を絞り、国が出しているデータと共に働き方先進国と呼ばれるドイツと比べてみる内容になります。(ただ、私自身が建築の現場で働く人間なので、建築に絞った記事になっているのはご了承ください。)
働き方改革とは
まず、働き方改革に関して知っておかなければいけませんね。
働く人の視点に立って労働制度の抜本改革を行い、企業文化や風土を含めて変えようとするもの。働く方一人ひとりが、より良い将来の展望を持ち得るようにする。
首相官邸HP
簡単に言ってしまえば、働き方改革とは多様性のある働き方が尊重された上で労働生産性の向上を目指す改革になります。
さらに日本の抱えている問題の『長時間労働』『人口減少による人手不足』『生産性の向上』を解決していこうという取り組みです。
しかし、簡単な問題ではなく長年の体制と、企業側と労働者側の対立の関係(企業側をよくすれば労働者側で悪くなる又逆も然り)は問題解決が出来るのか疑問でしかありません。
それはつまり様々な企業で休みが少なく長時間労働は当たり前のようになっている現状で、現状の生産性を維持しながらできるのかということです。
建設現場で
その長時間労働に関しては建設業界でも深刻な問題になっています。
2017年3月に東京国立競技場で働いていた従業員が過労自殺した悲しいニュースもありました。
過労の原因は1ヶ月間の残業時間が211時間56分にも及んだからだと言われています。
過重労働を強いていた下請け業者からすれば元請け業者に急がされていた事情なのにもかかわらず下請け業者は何もいうことはできない。
そして叫ばれる人材不足。
これは長年続く建設業界の仕組みに問題があるということになります。
果たして、これらの問題を働き方改革で変えることが出来るのでしょうか。
私は疑問に思います。
長時間労働の実態
まず長時間労働の実態についてのデータを用意しました。
各業種の労働時間の状況
1年間のうちで1ヶ月のの時間外労働時間が最も長かった正規雇用の従業員の『月間時間外労働時間の企業の割合』について、月80 時間超えと回答した企業の割合は全体 で( 22.7%)
業種別にみると『情報通信業』(44.4%)『学術研究,専門・技術サービス業』 (40.5%)、『運輸業,郵便業』(38.4%)となっています。
次に正社員の平均的な1週間当たりの残業時間について、業種別にその平均をみると、『運輸業,郵便業』(9.3時間)『教育,学習支 援業』(9.2 時間)『建設業』(8.6 時間)の順に多くなっています。
また、その残業時間が 20 時間以上と回答した労働者の割合は『運輸業,郵便業』(13.7%)『建設業』(12.9%)『教育, 学習支援業』(12.8%)の順に多くなっています。
企業に聞いた残業になる理由
残業になる主な理由としては『顧客(クライアント)からの不規則な要望に対応する必要があるため』『業務量が多いため』『仕事の忙しい時と暇な時の差が大きいため』『人員が不足しているため』を挙げる企業が多いです。
建設業では顧客からの不規則な要望に答えるというのは当たり前で断ることはほとんどしません。
それは元請けの現場監督さんも大変で一人で現場何件も抱えていることも知っているのでミスが起きても『お世話になっている』ということで受け入れます。
情報通信業でも同じでクライアントが要件定義に書いてないことを付け足ししてくるなど『不規則な要望』に答えなくてはならないようになっているとのこと。
それに『保守』『バグ』『エラー』なんかも突発的な仕事になって残業に繋がるケースもあります。
厚生労働省 平成28年版過労死等防止対策白書 参考 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/dl/16-1-2.pdf
残業なしで労働生産性をあげることは可能なのか?
次に海外と比べて日本の労働はどうなのかを見ていきたいと思います。
一人あたりだと低い日本
まず国内総生産(GDP)から見ていこうと思います。日本のGDPは2016年:4兆9386億ドル(543.2405668兆円)で世界第3位です。
1位と2位は大国であるアメリカと中国に対して、日本は小さな島国でこれだけのGDPの数値を出しているのだから仕事での効率が悪いわけがないと思っていました。
しかしGDPの総額を人口で割った数である一人あたりのGDPでは約38,917ドル:日本は22位なのです。
この数値は経済的豊かさの指標としても使われるそうですが、低さとしては先進国では最下位になってしまっています。
ただ、これでも伸びた方でその前までは減少していく一方でした。
よく比べられるドイツ
最近、NHKでドイツと日本の働き方を比べる放送がありました。
両国の共通点は多く、学者のコラムにも度々日本と比較して載せているのを目にします。
おそらく戦後のどん底からGDP3位の日本と4位のドイツになるまでに急速に成長させてきた発展と、不安定なEUを含む世界経済を牽引している事に加えて、両国の問題点も似ている点もあるからだと思います。
例えば、人口減少の問題です。
人口減少は両国とも深刻な問題で、2015年から過去5年間の人口1000人当たりの新生児の出生率を調査した結果、ドイツは新生児の誕生が8,2人で、日本は8,4人となりました。(参考 イギリス12,7人・フランス12,7人)
しかし、日本とドイツでは経済発展に関してドイツの方が苦しい状況にいたような気がします。
それは、ドイツは1990年まで東西で別れていましたし、『移民問題』『テロ問題』で国際情勢が揺れる中での発展でした。
加えて、人口も国土も日本の方が大きい数値となっています。なのにもかかわらず、1人当たりのGDPはドイツの方が約41,902ドルと日本を上回っています。
貧困率(相対的貧困)に関しては日本が16,1%でドイツは9,1%とかなり大きな差が出ています。
(民進党調査 参考)
日本とドイツの働き方
労働生産性を見ると、ドイツは日本と同じ時間働いたとして1.5倍ほどドイツの方が生産性が高いことがわかっています。
主に言われる理由は『残業は悪である』という価値観と労働時間貯蓄制度により精神的にもパフォーマンス向上に繋がり、短い時間での生産性を高めていると言われています。
つまりドイツでは残業すなわち労働時間が長い人は仕事を片付けられない無能な人とされ、短い時間で仕事をこなす人を短時間で仕事をこなす優秀な人と評価されるということです。
労働時間貯蓄制度というのは、銀行と同じような仕組みで、残業した分を別の日にあてて、その分早く帰ることが出来る制度です。
しかしながらプレミアムフライデーさえも導入されない企業が多い日本において労働時間貯蓄制度が導入出来るとは思えませんし、「仕事が片付けられないから無能」と言って突発的な仕事を与える企業にも問題があるわけです。
ワークシフト
長時間労働に関する問題点というと国の政策・制度設計・少子高齢化・人材不足などがあると思います。
また、労働生産性が低い問題も企業の問題・従業員の問題などがあります。
しかし、日本が長時間労働なのにもかかわらず労働生産性が低い大きな原因は、昔からの日本の働き方の構造である『上司が仕事を教えて、育ててから仕事を与える』という一連のプロセス自体に原因があるのではないかと思います。
例えば、ラズロ・ボック氏著【ワークルールズ】を参考にしていうと『がんばれ!ベアーズ』戦略というトレーニングをしてスーパースターを作るのではなく、ヤンキースのような特化した分野で結果を出した優秀な人材を雇う採用方法に変えた方が働き方がよくなるのではないかという考え方です。
安く雇ってトレーニングして一人前に育てることは効率がいいように見えますが、時間もかかるし、その期間上司は部下の面倒を見なくてはいけません。見ている最中は仕事ができないので生産性は低くなります。
そのような働き方に変えると失業者が多く出ますがベーシックインカムを導入することで回避できますし、失業者は労働生産性の数値にカウントされないので生産性の数値は上がります。
もう一つの方法は最新のテクノロジー(AI・ビックデータ・量子コンピューター・ロボット)を利用して突発的な仕事を防ぐもしくはサポートするシステムを構築していくことだと思います。
しかし、これもまだ実用化に向けて実装するまでは何年も先だろうと思います。
それともう一つ。
無料サービスが多過ぎることです。
ブラック企業を作る構造はブラックユーザー達にあると私は考えています。
例えば、海外ではコンビニの袋は貰えません。
もし、日本で袋に入れて貰えなかったら怒り出す一般ユーザーが続出することでしょう。
また、電車が遅れたり、ビールを持ってくるスピードが遅かったりしただけで激怒するユーザーもいますよね。
それらも海外では当たり前のように遅れます。
でも謝ったりなんかしませんよ。
過度なサービスがブラック企業を作り出している可能性について一般ユーザーも少し考える必要があるのではないかと思います。
最後に
いかがだったでしょう。
「これをすれば解決する」なんて解決策は存在しませんが、少しずつでも労働時間が短くなり、過労でストレスで自殺する人が少しでも減ったらと思います。
ただ、企業から見てる目線と従業員から見てる目線は違うので、企業と労働者の両方ともWin-Winになることは可能なのか、とても難しいことだと思います。
そんな難しい問題を国の政策一つで本当に変わるのか。むしろ、国、企業、働く人の全員で考えるべき問題なのかなと思います。
読んでいただきありがとうございました。
参考番組 NHK